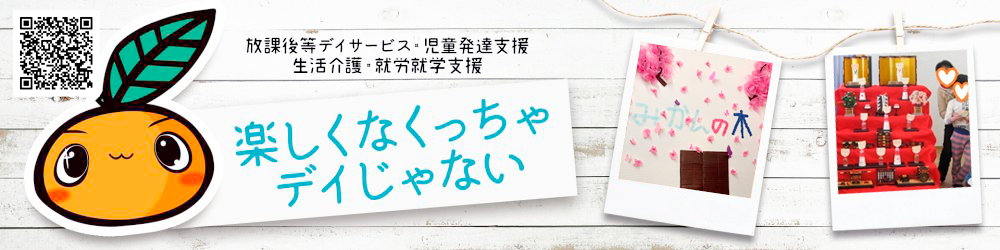竹谷店では今、SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)の一環として「どっちがカッコイイ?」カードを取り入れています。

中には「カッコイイ」カードと「カッコワルイ」カードがセットで入っており、物を食べている時は喋らない、廊下は歩く、待ってる人の列には横入りはせず後ろに並ぶ…といった日常生活の暗黙のルールやマナーをゲーム感覚で学ぶことが出来ます。

最近ではただどちらがカッコイイかを聞くだけでなく、何故それがカッコイイのか、こちらは何故カッコワルイのか、それではどうすればこちらのカッコワルイ子はカッコよくなれるのか…といった事も聞いていますが、結構な割合の子どもたちがしっかりと答えてくれています。

室内遊びの時間やトイレに並ぶ時なども
「さあ、どうするのがカッコいいかな?」
「カッコよく並んでるのは誰かな?」
と声掛けをすると、それだけで「カッコよく」なれる子どもが多くなりました。
この「カッコイイ」という言葉は非常に曖昧で、子どもたちが「カッコよく」なるためには自分の中でその言葉を整理し、含蓄された社会的規範等に当てはめ、更にそれを行動に移すという所まで出来なければなりません。
発達のゆっくりな子どもにはこれら一つ一つの行動が難しく、どうするのが「カッコイイ」のか分からなかったり、分かっていても衝動を抑えきれなかったりといった事が多いものですが、竹谷店ではだんだんと「カッコよさ」を自分で考え、そして自分を律する事が出来る機会が増えてきたように思います。
大人の目から見るとつい出来ていない事の方に注目してしまいがちですが、少しずつ子どもたちは成長しています。昨日より少し良くなっている所に目を向け、長く暖かい目で見守ってあげて下さい。