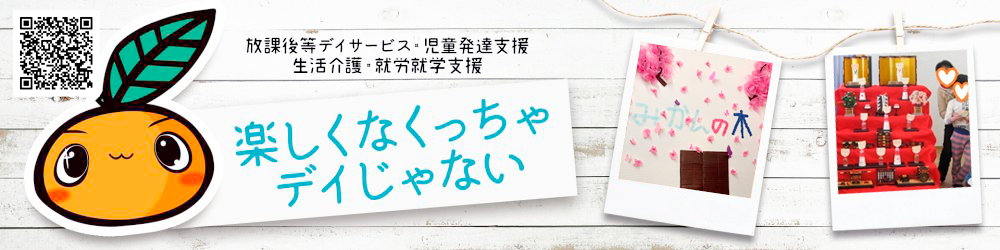みなさま、こんにちは。新学年を迎え、子ども達も新しい環境に慣れてきた頃かと思います。杭瀬の子ども達は小学一年生から二年生に進級しました。今までは自分たちが一番下で上級生にお世話していただく立場だったのが、新一年生が入学してくることによって今度は自分達がお世話してあげる番になり、ちょっぴりお姉さん、お兄さんになったようですね。
① 音楽療法
月に1回ある音楽療法を子ども達は楽しみにしています。毎回、新しくなっていて、音楽に合わせて体を動かしたり、クイズがあります。何よりも楽しみにしているのが、触れることができる教材があることです。珍しい楽器や、手作りのボールや絵本と連動した遊びがあり、毎回違うのです!!
『今日は何だろう?』という感じでみんなワクワクしています。


見ているだけでなく、実際に触って自分で演奏できるのが音楽療法の醍醐味です。 その音を出すときに周りと合わせながら演奏することで綺麗なハーモニーが出来上がります。子ども達は初めてマンドリンを触って興味津々です。この音楽療法で初めてを経験することがたくさんあります。



クラス全員でする活動と一人ひとりがする活動が上手くバランス良く組み込まれていて、楽しすぎていつもあっという間に時間が過ぎてしまいます。

終わったばっかりですが、みんな次の音楽療法を楽しみにしています。
② 文章聞き取り訓練 & 指先の巧緻性
みかんではいつも終わりの会の前に絵本の時間があります。(よほど時間がない場合は除きます)
子ども達が飽きないように、職員が図書館へ借りに行って毎回違う絵本を読んでいます。
今回の課題は絵本の読み聞かせをしたのですが、いつもとは違い読み終わったあとに本の内容に関する質問をしました。

真剣に聞き入る子ども達。職員の読み聞かせにも工夫が凝らされています。大袈裟な表現は避け、子ども達が集中しやすいような速さで一人一人とアイコンタクトを取りながら読み進めます。

内容理解の質問に答えるのはそう簡単ではありません。 まず、話の大まかなストーリーが分かっていないと答えにくいです。積極的に手を上げて発表してくれたり、分かっているけど手を挙げるのが恥ずかしくてじっと見ている子ども達もいました。 私たち職員がこの質問は難しいかな?と思っていた問題もしっかり答えることができる子ども達もいました。内容理解の質問は答えることができるのが重要なのではなく、子ども達が『何だったっけ?』と聞いた話を振り返り思い出そうと考えることがこの課題の本質です。そうすることで記憶力や記憶の定着が促進されるからです。
もう一方のグループは巧緻性を高める訓練です。巧緻性(こうちせい)とは指先の器用さを意味します。巧緻性と学力には密接な関係があるといわれていますが、私たちが巧緻性に重きを置くのには別の理由があります。巧緻性が高いと生活しやすくなると言われているからです。手指の巧緻性を研究する川端博子教授(埼玉大学)らが2007年、小学6年生518名を対象に実施した調査によると、巧緻性を測定する「糸むすびテスト」で成績が上位だったグループは、そうでないグループと比べてさまざまな学習活動を楽しんでいた そうです。
学校で同じことをするとしても、楽しんでするのと 苦手意識を持ちながらするのでは雲泥の差が出てきます。子ども達が生活しやすくなるようなお手伝いができることを願ってこの課題を作りました。
かわいいライオンさんに洗濯バサミの立髪をつけていきます。大人にとっては簡単なことですが、この年の子ども達にとっては 力を入れ目標の場所まで持続させ離す という一連の動作は意外に大変なのです。 かわいい動物に興味をそそられ集中して取り組んでくれました。

こちらは 赤、青、黄、緑色の枠に同じ色のゴムをかける訓練をしてもらいました。今度は色の認識の要素も入ってきて少しグレードアップしています。最初は上手くできなくて不機嫌になっても、回を重ねるたびに上手くできるようになり、全部できると誇らしげな笑顔を浮かべていました。

今後も 指先の巧緻性に関しては 継続的に進めていく予定です。